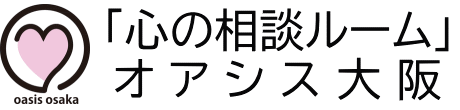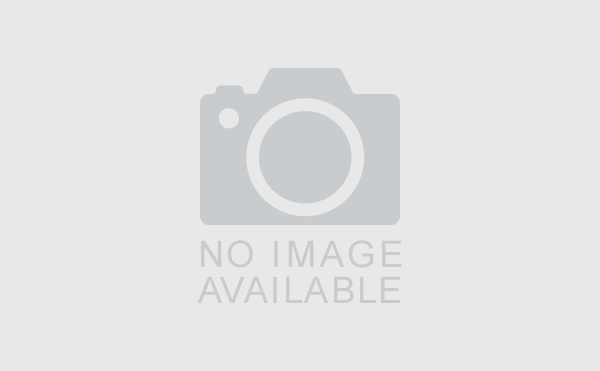「あるがまま」という言葉は使わない~神田橋條治先生の言葉
「あるがまま」という言葉は使わない~神田橋條治先生の言葉
例えば、発達障害や統合失調症、双極性障害等の精神病とレッテルを貼られた方や
自分の性格で悩んでいる方・・・。
「あるがまま」の自分を受け入れよう(周囲は受け入れさせよう)としても
中々それができない方もいらっしゃると思います。
僕もそこには「諦めろ」という意味や治らなくっても「仕方がない」といった
援助者側の責任逃れなニュアンスを感じてしまいます。
カリスマ精神科医の神田橋條治先生はご著書の中で
「僕は”あるがまま”という言葉は使わない。その言葉には何か動かない様な
イメージがある。希望や期待や夢が入り込む余地が減る言葉は使わない。
それらが増える言葉をいつも使う」とお書きになっています。
実際先生は「発達障害は発達する」と仰っていて、例えば「空気が読めない」
で困っておられる方がいても「その能力が元々備わってないから無理だ」とは
考えずに「空気が読める能力は、今はどういう機能として発揮されてるのだろう?
例えば、自分の体調に対する過敏性を社会で使えるものに磨いて行けば、
活用できるはずだ」というお考えの基で、1日50人もの患者さんを
”魔法”の様に治療されて来られました。
先生のご著書から推察すると、その”魔法”は、たぐいまれな観察能力
(写真だけでも、身体の歪みから脳のどの部分が圧迫されて活動を阻害されてる
のかが、おわかりになる様です)とそれに伴う診立ての的確さ、
患者さんにとって役に立つものは全て使う(恐らく心理学のあらゆる流派を
踏まえておられ、漢方処方や整体、 バッチフラワーレメディー等の民間療法まで
実にお詳しい)といった柔軟さも、ただただ敬服差し上げるのみです。
そして、何より臨床の現場で「どうやったら目の前のこの人を治せるか?」
と常に考えられて実践して来られた「現場で身につけたスキルと考え方」は
ただただ”凄い”の一言です。
僕も援助者の端くれとして、観察力を磨き、クライアント様の持っておられる能力
をいかに活用し、目の前の方に有効な手段なら何でも使う、という姿勢を
もっともっと”発達”させて行きたいと思います。
プロフィール
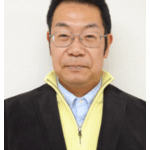
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する