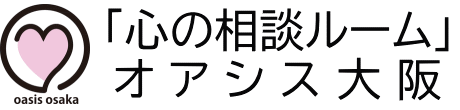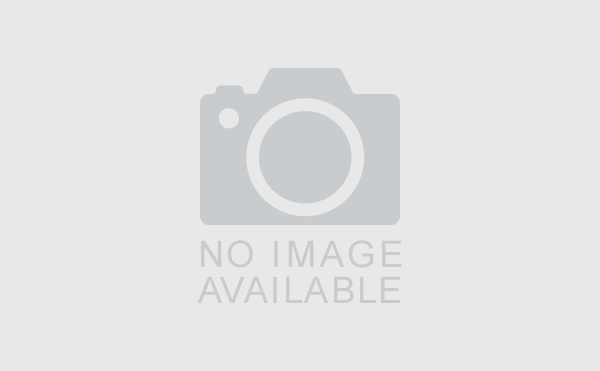フロイトの原因論,アドラーの目的論,そんなの関係ない論③
フロイトの原因論,アドラーの目的論,そんなの関係ない論③
前回、前々回に引き続いて「フロイトの原因論」と「アドラー目的論」
と「そんなの関係ない論」について。
今回はそれら3つの論を臨床現場で活かす際の注意点を
僕のやり方に沿ってお伝えします。
例えば、独り暮らしを始めてから過食等の症状が発症したクライアントさん
がいたとします。
その場合は、まず「そんなの関係ない論」に沿って、
症状を維持しているパターンを壊す介入を行います。
(解決志向、MRI、NLP等)
それでも効果が出ないのであれば、
「目的論」に沿って、「もし症状が無くなったとして直面する不安は何か?」
を探って頂きます。
もしここで症状が果たす役割に気付かれたら、
⇒例えば「症状がなくなったら、お母さんともっと離れてしまう気がする」
その方の中の「症状に反対する部分」と「症状に賛成する部分」との対話
を通じて折り合いをつけて貰います。
⇒例えば 二つの”部分”同士を対話させた後に、統合的な部分の立場で
「”症状に賛成する部分に”、もっと甘えたかったのに甘えられなくて辛かったね」
等と共感し、「なのに、あなたの事を嫌ってゴメンね。
よく頑張ってその辛さを耐えて来たね。有難う」
「症状という形ではなくて、あなたの目的が叶える為にはどんなやり方がある?」
等と、ゲシュタルト療法やNLP等を組み合わせて使う等。
それでも折り合いがつかなければ、「原因論」に従って
親等に対する未完了の事柄を完了させる援助を行います。
(フォーカシング⇒ゲシュタルト療法、インナーチャイルド癒し等の
イメージワーク)
更には症状に賛成する部分が持っている非適応的思考を変えてゆくお手伝い
をします。(ビリーフチェンジ、スキーマ療法等)
※実際は平行して行う事が多いです。
勿論、同じ様な症状でもクライアントさんによって当然異なりますので、
どれか一つの論に沿ってセラピーする場合もありますし、
家族療法的なアプローチや認知行動療法的なアプローチが必要な場合もあります。
但し、3つの理論の様々な学派の考え方を折衷して使う場合は細心の注意
が必要です。
例えば、症状を外在化してナラティブアプローチ的に入った場合は、
後で目的論に戻そうとしても、「症状」と「自分」を一旦切り離した後で、
それを再び内在化して「ごめんね。有難う」等と折り合いをつける事が
できなくなってしまいます。
まるで「憎い敵」に手の平を返した様に謝罪し感謝する様なものです。
折衷する場合は、兎に角経験を積んで行って、クライアントさんに合わせて
細心の注意を払わないといけないと実感しています。
プロフィール
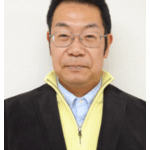
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する