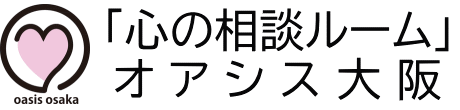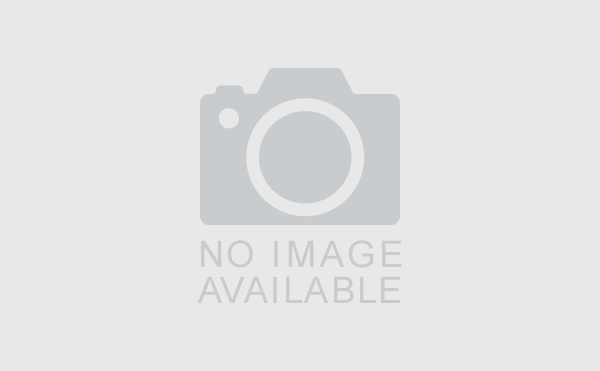愛着形成と愛着の回路⑧愛着の回路を形成するヒント(3)
愛着形成と愛着の回路⑧愛着の回路を形成するヒント(3)
前回お書きしたヒントを基に、
自分の中の「親の部分」と「子供達の部分」それぞれに名前を付ける事
ができれば、
今度は、
それぞれの部分が一体化しない様に距離を保ち続ける工夫が必要
だと思います。
例えば、
母親が我が子の不安に巻き込まれてしまって、
自分まで不安になってうろたえてしまえば、
不安を和らげてくれる存在が居なくなります。
ですから、
「親の部分」は「子供達の部分」の強烈な感情や感覚、思考に呑み込まれずに
距離を保ち続ける必要があります。
今回は、その為のヒントをお書きしたいと思います。
⑧愛着回路を(再)形成する(3)
(3)自分の”親の部分”(大脳皮質側)と”子供達の部分”(大脳辺縁系側)の
距離を取る
A何らかの引き金によって、
身体的な変化(体の緊張・硬直、心臓がバクバクして呼吸が速くなる、
頭が真っ白になる、言葉が出て来ない等)
や
感情の変化(不安・恐怖、怒り、悲しみ、寂しさ、無価値感、自己嫌悪、
罪悪感・恥、希死念慮等)
が生じた時に、
「子供達の部分」の誰かが活性化したと意識しましょう。
Bそして”どの子”が出て来たのか?を感じ、考えてみます。
例「私の中の”寂しがり屋さん”が泣き始めて、
”怒りんぼちゃん”が出て来てる」
等々。
C特定できた”その子”の訴えを聴きましょう
例「怒りんぼちゃん、何を怒っているの?」
⇒「だって、私の妹の”寂しがり屋さん”が淋しいよって泣いてるのに、
ママ(彼氏)は傍に居てくれないの。
だから私がママに”何でこの子を放っておくのよ?!”って叱ってあげたの
・・・」
ここまでで大切な事は、
・”親の部分”は感情的・感覚的な”子供の部分”に決して巻込まれずに
冷静に距離を取る事、
・”子供の部分”のどんな訴えも決して否定せずにちゃんと聴いてあげる事
だと思います。
(余裕があれば”子供の部分”の訴えを紙に書き出してみるのもいいでしょう)
#愛着障害のカウンセリングについては、
こちらにお書きしてますので、ご参照ください
プロフィール
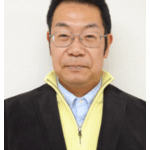
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する