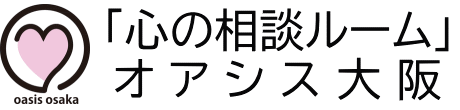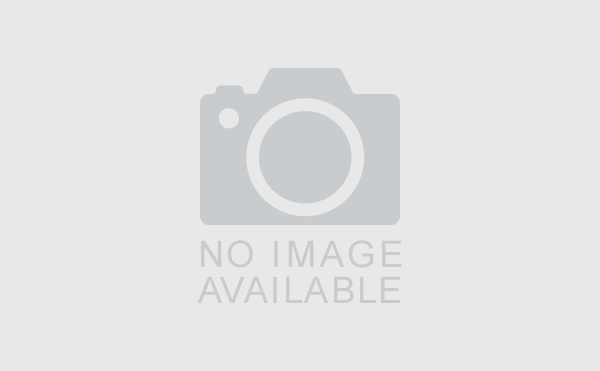後悔を残さない人生にするヒント③後悔のワークの注意点
後悔を残さない人生にするヒント③後悔のワークの注意点
前回の
「②」のワーク
や
前々回の
「①」のワークをやろうとしても、
(Ⅰ)「そんな恐ろしいイメージは怖くてできない」と感じる方
や、
逆に
(Ⅱ)「何も感じない」等と、リアルにイメージできない、
とか
(Ⅲ)「よし!今日から悔いが残らない様に生きよう!」
等といったモチベーションが上がらずに
結局は元の日常に戻ってしまう
という方もいらっしゃると思います。
それは何故なのか?
「ポリヴェーガル理論」を基に私の考察をお書きしたいと思います
まず、
上の
「(Ⅰ)」の場合は、
その”恐ろしいイメージ”が
腹側迷走神経系による交感神経系の制御(感情調整)が効かなくなって
(耐性領域の上限を超えた)、
過覚醒状態になり、”逃走/回避”という防衛機能が働いたと考えられます。
次に
「(Ⅱ)」の場合は、
その”恐ろしいイメージ”が
腹側迷走神経系による背側迷走神経系の制御(感情調整)が効かなくなって
(耐性領域の下限を超えた)、
低覚醒状態になり、「フリーズする」という防衛機能が働いた
と考えられます。
(勿論、単にイメージが苦手だという場合もあるでしょうが)
更に
「(Ⅲ)」の場合は、
その”恐ろしいイメージ”をもってしても
腹側迷走神経系による交感神経系や背側迷走神経系の制御が
”余裕”で耐性領域内で行われ、
それらの神経系からの強い感情や感覚等がボトムアップしてくる事も無く、
結果としてモチベーションが維持できない、と考えられます。
つまり、
この「後悔のワーク」を効果的なものにする為には、
「腹側迷走神経系による交感神経系や背側迷走神経系の制御を失う事無く、
耐性領域内で行う」事
と
「かと言って、特に交感神経系や背側迷走神経系が機能しない状態
では効果が無く、
それらの神経系から強い感情や感覚等がボトムアップしてくる様な
耐性領域”ぎりぎり”の範囲で、イメージしてゆく事が必要」
が大切だと思います。
例えば、
お気に入りのホラー映画を観た時。
上映中は手に汗握ったり、恐ろしくて声が出そうになったり、
心臓がバクバクしたり、身体が固まってしまったり声が出せない、
等という変化が起きるでしょう。
これはつまり、
交感神経系(過覚醒)や背側迷走神経系(低覚醒)が刺激されて、
生理的変化や恐怖や不安といった強い感情がボトムアップ
(自然と湧き上がる)されているという事です。
所が、
そんな中でもポップコーンを頬張ったり、隣の恋人と会話できるのは、
腹側迷走神経系がぎりぎりの状態でそれら2つの神経系を制御できていて、
かろうじて耐性領域内に収めているからと言えるでしょう。
そして、
映画を観終わった後も、湧き上がってきた身体感覚や強い感情は
暫くは続くでしょうが、
そのうちに腹側迷走神経系の働きが優位になって、
それらの強い反応は治まってゆき、
普段通りの日常生活を送れる様になるでしょう。
次回は、
この事を踏まえて「後悔のワーク」の”コツ”を
お書きしたいと思います。
プロフィール
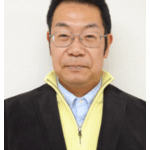
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する