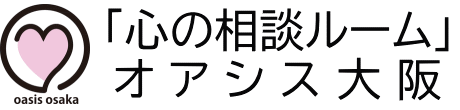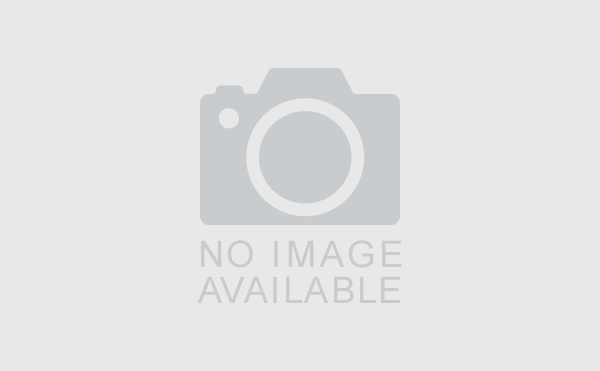多重人格障害(解離性同一症)のメカニズム
多重人格障害(解離性同一症)のメカニズム
今回は、
前回までの多重人格障害(解離性同一症)の考えられる原因
に基づいて、その”発症”のメカニズムを推察してみました。
前回までにお書きした様に、
先天的に「感覚過敏」や「解離のし易さ」という遺伝
の影響を受けている人が
幼少期に「虐待」や「ネグレクト」等の不適切な養育
を受けて来た場合、
交感神経系による「闘争・逃走反応」
や
背側迷走神経系による「凍り付き反応」
が繰り返され続けるでしょう。
それはつまり、
「交感神経系の亢進」⇒「背側迷走神経系の亢進」が
何年間も毎日続いてゆくという事になります。
それはまるで、
いつやられるかわからない戦時下に取り残されたかの様でしょう。
だとすれば、
目標を立てたり、考えたり、何かに興味・関心を持ったり、
遊んだり、友達と楽しんだり、なんて余裕は無くなり、
「前頭前野」は機能低下してゆくでしょう。
(※複雑性PTSD、発達性トラウマ障害と言われる状態)
そしてそうなると
「凍り付き反応」や「闘争・逃走反応」に纏わる
サブパーソナリティー達が
容易に前頭前野を”乗っ取る”事になるでしょう。
それはまるで、
個性的な子供達が集まった小学校のあるクラスで、
今迄は担任の先生が、暴力的で大騒ぎしてる子を
落ち着かせたり、
落ち込んでいる子を元気づけたり、
甘えたさんな子を甘えさせたり、
怖がって泣きじゃくっている子を
安心させたりしていたのに、
先生が突然意識を失い、
それと同時に教室内は手が付けられない混乱状態になった、
つまり、子供達に乗っ取られたそのクラスは制御を失い、
無法地帯と化してしまった・・・
という様なものだと思います。
そして恐らくそういった家庭環境の中で育つ子供は
「凍り付き反応」がベース(デフォルト)で、
「闘争・逃走反応」や甘えたりする「愛着を求める反応」
は無意識の底へと抑圧されてしまうでしょう。
そんな時に、前回・前々回にお書きした様な、
解離し易い、或いは感覚過敏の遺伝子を持っていたり、
エピジェネティクな遺伝の影響を受けていると、
ベースの「凍り付き反応」の中に
「解離」を司るサブパーソナリティが造られ、
前頭前野がそのサブパーソナリティに乗っ取られ、
その間の現実認知や記憶も阻害されてしまうかもしれない。
更に、前頭前野が脆弱化している訳ですから、
無意識に抑圧された、「闘争」「逃走」「愛着」等に
まつわるサブパーソナリティ達も、「ここぞ!」とばかりに
代わる代わる次々と前頭前野を”乗っ取って”ゆくでしょう。
そうなると、
担任の先生が倒れ、無法地帯と化した小学校の生徒達に、
好き勝手な言動が益々増えてゆく、というたとえ話と同じ様に、
サブパーソナリティの”各自我”が強化されてゆき、
それぞれが別々のパーソナリティを自由に表現する様になる
でしょう。
解離性(同一性)障害は、解離障壁がある為、
それぞれの交代人格が分断されて、記憶が共有されず、
自己同一性が損なわれると言われますが、
私は、
自己同一性を保つのに必要な前頭前野が
まず解離を司るサブパーソナリティに
乗っ取られて機能低下し、
次々と「闘争・逃走」や「愛着を求める」
サブパーソナリティ達が、
入れ替わり立ち代わり乗っ取ってゆくから
記憶の共有や自己同一性が損なわれる
のでは?と考えています。
次回からは
多重人格障害(解離性同一症)の治療法
についてお書きしてゆきたいと思います。
#解離性(同一性)障害のカウンセリングについては、
こちらにお書きしてますので、ご参照ください
プロフィール
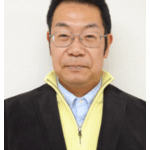
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する