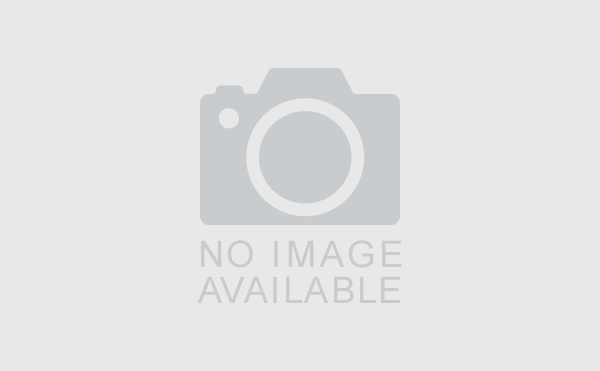カウンセリングで大切なポイント⑦働きかけるポイントを決める(1)
カウンセリングで大切なポイント⑦働きかけるポイントを決める(1)
<前回からの続き>
<⑦悩み/症状の解消の為に働きかけるポイントを決める(1)>
CLさんの今のお悩みや症状の根本原因が推測できれば、
働きかける(介入)ポイントを決めてゆきます。
まず今回は
架空の例で、根本原因(と思しきもの)を推測してみましょう。
例えば、
「彼氏にLINEを送っても、すぐに返事が無い。
”見捨てられるかも?”と思って、
彼が仕事中であろうがLINEを何十通も送ったけど、既読が付かない!
許せなくなって彼の職場に電話をして、
彼を呼び出してもらいブチギレた。
彼は”仕事中だぞ!”と冷たくあしらったので、
”死んでやる!”とオーバードーズとリスカをした。
そんな事が続いた或る日、
彼が”もう終わりにしたい。別れよう”と言ってきた。
私は”ゴメンなさい、ゴメンなさい”と泣きながら何度も謝って
彼にしがみついた・・・
前の彼氏の時も、その前も同じ様な状態になって、
結局別れる事になった。
彼に
”お前、病気と思うから、病院に行け!
それでも治んなかったら本当に分かれる”
と言われたので、
仕方なく病院に行ったら”境界性パーソナリティー障害(BPD)”と言われた」
といったCLさんの場合。(架空の例です)
ヒアリングとアセスメントによって
想像を巡らせ原因を遡ってみますと、
(1)家族歴・成育歴等から、
BPDと関連すると考えられる愛着の問題(とらわれ型、未解決型等)
や肉体的・精神的な虐待やネグレクトは余り無さそう。
(2)だとすれば、
何故自己像が不安定で、感情の制御が不可になっているのか?
(3)それは、恐らく自己客観視と(感情等を司る)神経系の自己調整能力
に問題がある
(4)だとすれば、それは何故か?
(5)それは、
自己客観視に必要な背外側前頭前皮質の発達が遅れているから?
(6)だとすれば、それは何故か?
(7)父親も似た気質だった様で、遺伝要因が働いてるのかもしれない。
(8)もしそうなら乳幼児期から感情や感覚に圧倒され、
益々背外側前頭前皮質の発達が阻害され、
母親との愛着が安定型だったとしても
(自己客観視不可の為)内的作業モデルが作られずに
自己調整できないままになった?
(9)そうだとすれば、腹側迷走神経系による神経系の自己調整機能である
”耐性の窓”を拡げる事はおろか、
それ以外の部分である(”偽”耐性の窓と呼ばれる)交感神経系と
背側迷走神経系の防衛反応によって神経系を制御しようとして、
かろうじて社会生活を保てるレベルに保ち、
それが習慣化してしまっている
(10)その様に自己調整力が身につかないと
「見捨てられるのでは?」等の不安が益々強くなり、
防衛反応も益々強化され、
それに基づいた言動を採る(相手への理想化とこきおろし、執着、
自傷行為等)為に結果として見捨てられて、
「私は誰からも愛されない」等のスキーマも強化され、
益々不安が強くなり、それ故、防衛反応も益々強くなって
自己調整不全が酷くなってゆく、という悪循環に陥るでしょう。
次回はこの”例”に基づいて、
CLさんに働きかける''(介入)ポイントを決めてゆきます''。