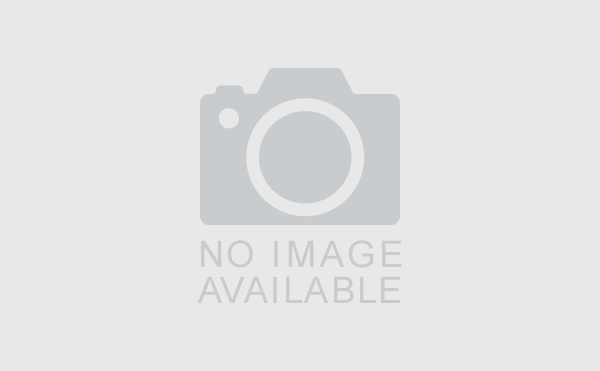我慢する事について⑦我慢し過ぎて苦しんでる人(2)
我慢する事について⑦我慢し過ぎて苦しんでる人(2)
今回は、
前回分類したタイプの「(2)」の
「元々我慢が苦手な人が後天的に我慢する習慣が身についた」為に
我慢して苦しんでいる場合についてお書きしたいと思います。
(2)元々我慢が苦手な人が後天的に我慢する習慣が身についた
以前からお書きしています様に、
「心を安定させる方向性」として、
①不快刺激を取り除く(セロトニン型)
②快刺激へ意識をシフトさせる(ドーパミン型)
③他人との交流を利用する(オキシトシン型)
の3つのタイプがあり、
人によってその適正な比率/割合は恐らく生まれつき決まっている、
と私は考えています。
ここで、
我慢が苦手な人は「②」や「③」の割合が強く「①」が強くない為に、
不快と向き合い、それを取り除くための我慢は苦手な筈です。
ところが、
我慢を強いられる様な被虐待的な環境で育った場合や、
敏感さによるトラウマ(例えば、我慢できない事を、他人に否定されたり、
恥をかいたりしてそれがトラウマになった等)を負った場合。
「もう二度と傷つけられない様に」といった防衛反応が生じ、
本来の自分を殺し、相手に合わせてゆく(服従)等の
背側迷走神経系の凍り付き反応が繰り返されるでしょう。
そうなると
「②」や「③」の主体性や自分らしさを失い、
本来の傾向とは違う「①」の不快刺激を取り除く為に我慢する習慣が
身についてしまうでしょう。
そして、
「我慢したくない(本来の自分)」
けど
「我慢しなきゃいけない(防衛反応)」
といった葛藤/ジレンマが生じて、生き辛くなると考えられます。
※この苦しみの解消にご興味がある方は、お気軽にご連絡下さい
次回は「(3)」の
元々我慢が苦手な人が目標を見失った為に
我慢して苦しんでいる場合についてお書きしたいと思います。