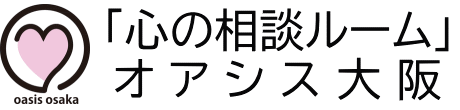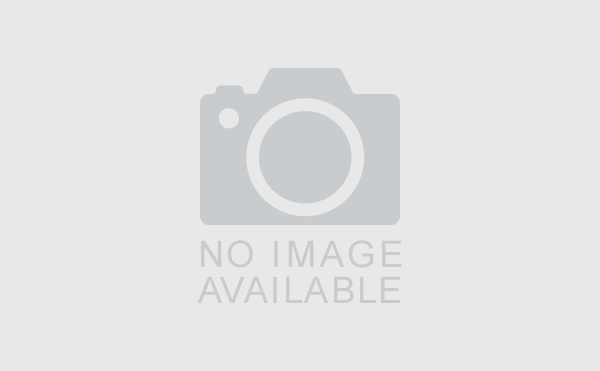多重人格障害(解離性同一症)の原因③後天的な環境因
多重人格障害(解離性同一症)の原因③後天的な環境因
今回は、
多重人格障害(解離性同一症)の考えられる原因の
「③後天的な環境因」についてお書きしたいと思います。
<多重人格障害(解離性同一症)の原因
③後天的な環境因>
幼少期に、身体的、或いは心理的な虐待を受けた場合
や
ネグレクト等の所謂「不適切な養育」(マルトリートメント)
を受けて来た場合は、
常に生命の危機を感じ続ける事になります。
その様な状況下では
脳・神経系・身体の防衛反応が働き続け、
交感神経系の「戦う・逃げる反応」によって
恒常的にストレスホルモンであるコルチゾール
(副腎皮質から分泌される)が分泌され続けるでしょう。
でも幼い子供にとっては、
親や養育者に対して、戦う事も逃げる事も叶わない
訳ですから、
(ポリヴェーガル理論で言うところの)
背側迷走神経系の「凍り付き反応」=オピオイドによる鎮静
に切り替わると考えられれます。
そして、
この「交感神経系の亢進」⇒「背側迷走神経系の亢進」
が何年間も毎日続いてゆく訳です。
解離性(同一性)障害と診断された人の研究で、
扁桃体(情動や恐怖に関わる脳領域)や海馬(記憶に関わる脳領域)
などの機能や構造に変化が見られたり、
トラウマ反応に関連する脳内の神経回路に何らかの偏りが生じている
可能性があると言われています。
私はそういった意見に対しては「そりゃそうだろう」と感じます。
何年間も毎日、
防衛反応にまつわる2つの神経回路が過亢進し続けていれば、
トラウマ記憶が保存されてゆく扁桃体は過敏になり、
(覚える、考える、等の前頭前野を使うどころではないので)
海馬は委縮してゆくでしょう。
加えて、
背側迷走神経系の「凍り付き反応」が生じてる時間が長い
でしょうから、
前頭前野が働く余地は少なくなってゆくでしょう。
しかも、
社会的な交流や安心・安全、成長や健康・治癒に関連すると
考えられている「腹側迷走神経系」は殆ど働く事ができなくなり
そういったポジティブな経験を積み上げてゆく事もできなくなる
・・・。
次回は、
多重人格障害(解離性同一症)の(私なりに考える)メカニズム
についてお書きしたいと思います。
#解離性(同一性)障害のカウンセリングについては、
こちらにお書きしてますので、ご参照ください
プロフィール
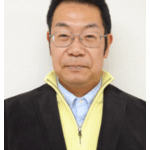
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する