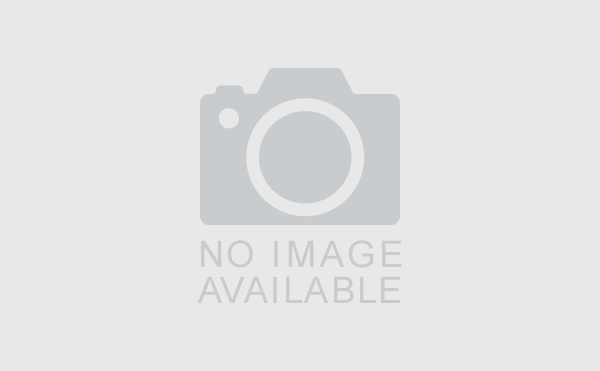何故超短期でのカウンセリングが可能なのか?③
何故超短期でのカウンセリングが可能なのか?③
今回は私自身のカウンセリングの特徴をお書きしたいと思います。
まず、
お客様とカウンセリングでの目標を作り、共有します。
同時にお客様のリソースを探ってゆきます。
そして前回までにお書きした、
①五感(或いはイメージ)での知覚(インプット)
②(それに纏わる)記憶の想起
③思考・意味づけの形成(認知)
④感情・情動の生起→生理的な変化
⑤反応・行動(アウトプット)
に関して、
目の前のお客様の現在の「①」~「⑤」のパターンを把握します。
そして、
「①」~「⑤」の中で一番のキーポイントで、
変えやすいと思われる所に的を絞ります。
但し、
「②」の部分のトラウマや「④」の部分の感情の抑圧が大きい
と思われる方には、その処理を優先します。
(でないと、そこが引っ掛かって行動変容に
結びつかない事もあるからです)
加えて、
最近特に重要だと認識している事が、お客様の気質や傾向です。
例えばHSPや発達凸凹の傾向をお持ちか否か?
の見立ては特に重視し、
その場合は真っ先に考えないといけない事は、
「①」のインプットを変える(例えば環境調整)という事だと思います。
ここを押さえておかないと「③」や「⑤」に働き掛けても、
うまく行かない「難治例」となってしまい、
短期での解決は望めないと思うのです。
その後、
「①」~「⑤」の中でターゲットとした部分を変える為に、
様々な方法でリフレーミングします。
(リフレーミングはとても大切で、お客様の腑に落ちないと、
変化されるのは難しいと思います。)
※これは、家族療法の場合も同様で、
例えば、親御さんが我が子の”問題”を相談に来られた場合、
親御さんのお話から、親御さんとお子さん
(或いはご主人や他の家族も)の気質・傾向、リソース、
コミュニケーションパターン等から見立てをきっちりとし、
お子さんの「①」が変わる様に
親御さんの「⑤」が変わる様なリフレーミングを用いて介入してゆきます。
そして、
リフレーミングがうまく行くと、お客様はその部分を変えていこうとされます。
(その為に必要な簡単な課題をお出しします)
ここで、もしうまく行かなかった場合は、
「①」~「⑤」の中の他の部分に働き掛けます。
つまり、ターゲットは「①」~「⑤」の5つだけですので、
見立てを間違えずにリフレーミングがうまく行けば、
1~3回程度の面談の間に、お客様が望まれる方向へ
自ずと変化してゆく訳です。
では、
「日常生活での変化の定着(般化)はどうなるのか?」という問題ですが、
それに関しては、
「何故うまく行きましたか?」
「これができたら、次はこうして行きませんか?」
等と、「何故変化したのか?」「変化を継続したり
次の段階ではどう考え、どうしてゆけば良いのか?」という具体策を、
心理教育的に個々人に合わせてお伝えしますので、
後は実生活で実践して頂き、
ヒントが必要な時にのみ、またお越し頂ければよい訳です。
勿論、全ての方が「超短期」を望まれている訳ではないと思います。
実際「ここで肯定してもらって1週間の励みになる」
と週1回お越しになる方や、
「唯一の相談相手・話し相手になってほしい」
「何回かかってもいいから、私の辛い思いを受け止めてほしい」
と定期的にお越しになる方もいらっしゃいます。
ですから、
「超短期」を望まれる方も、じっくり話を聞いて欲しい方も
ご興味がお有りでしたら、ご連絡下さい。