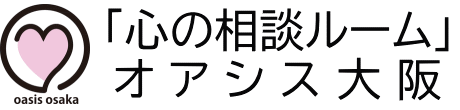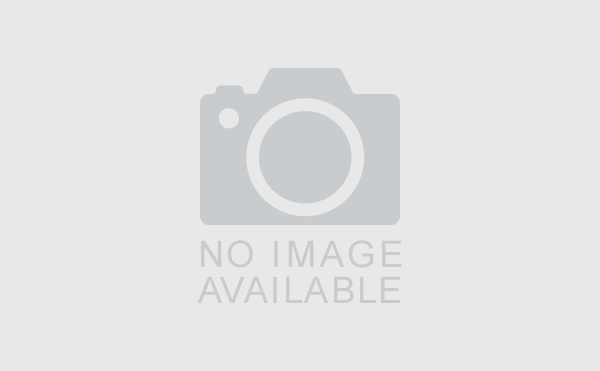HSS型HSPの人は何故モチベーションを維持しにくいのか?
HSS型HSPの人は何故モチベーションを維持しにくいのか?
「好きな彼女を口説き落として結婚した途端に冷めてしまった」
「ギャンブルで勝てないとわかっていながら止められない」
「痩せなきゃ!と思っても過食が止まらない」・・・。
特に刺激追究のHSS型HSPの人は、常に新しい刺激(ドーパミン)を
求めていると思われます。
そして、自分にとって「快」を感じる刺激を求めている時は
モチベーションが高まっていますが、
それを得てしまうと急速にモチベーションが下がってしまうと思われます。
では一体、何故そうなってしまうのでしょうか?
私の推測ですが、その鍵は快感をもたらす「ドーパミン」と
心を安定させる「セロトニン」という2つの脳内神経物質の働きが
関係しているのでは?と思います。
「これをすれば自分の目標が叶う」という時にはドーパミンが出て
モチベーションが高まりますが、
その目標を達成すれば「満足」=セロトニンが出ると思われます。
そしてこのセロトニンはドーパミンを抑制しますから、
ドーパミンは満足した瞬間に減少するでしょう。
となると、また新たにドーパミンを求めないといけなくなります。
上の例で言いますと、
彼女を口説いてる時には、”この女性を手に入れたら・・・”と
目標に向かってドーパミンが出てる訳ですが、
手に入って満足した途端にセロトニンによってドーパミンが
抑制されます。
だから、別の女性を新たな目標にして、
ドーパミンが出る方向へ向かうのではないでしょうか?
ギャンブルや過食も同様で大当たりして借金返済したり、
食事制限して目標体重に達したとしても満足してはいけない訳です。
何故なら満足した時点でドーパミンを得る術がなくなりますから。
しかもドーパミンに対しても「馴化」(慣れ)が起き、
より沢山の報酬(ドーパミン)を得られないと満足できなくなると思われます。
ですから「もっと(借金して)稼がなきゃ」とか
「もっと(体重を増やして)痩せなきゃ」等といった無意識の働き
によって、そこから抜け出せなくなるのでは?と思います。
そしてそれが簡単に手に入るものであれば、
そこまでモチベーションは高まらないでしょうし、
逆に「絶対に無理だ」と自分で思える目標に対しても
モチベーションは維持できないでしょう。
それは恐らく、
簡単に手に入るものであればドーパミンも一瞬しか得られないですし、
絶対無理な目標に対してはそもそもドーパミンは出ないでしょう。
つまり
「その目標を達成する可能性が高すぎてもダメだし、可能性がゼロでもダメ」
という事だと思います。
例えば前回の県大会で3位に入ったアスリートを例にすると、
「次の県大会で優勝するぞ!」は可能性はゼロでは無いが簡単では無いから
ドーパミンを得て、練習し続けるモチベーションが維持できる訳です。
でも県大会で優勝しちゃうと、それ以上のドーパミンが出なくなります。
だから「今度は国体で優勝しよう!」と更に可能性が低い目標を掲げ、
(困難な目標を達成すれば、より多くのドーパミンが得られますから)
ドーパミンの馴化を防いでモチベーションの維持を行うでしょう。
そしてそれも達成して「今度はオリンピックでメダルを獲るぞ!」
と更なるドーパミンを求める。
そしてそれをも達成してしまうと(その目標の延長線上でのドーパミン
を得る手段が無くなるので)モチベーションが下がってしまい、
引退してしまうかも知れません。
※私見ですが、強迫性障害も「安心したいから強迫行為を行う」
と考えられていますが、「安心」という目標の為の強迫行為には
ドーパミンが関わってるのでは?と考えています。
だとすれば、何故強迫がどんどん酷くなってゆくのか?
(=目標が高くなってゆく)、
何故日に何度も安心を求めるのか?(=一瞬でドーパミンが出なくなる)
がドーパミンの馴化で説明できるのでは?と思います。
だとすれば抗うつ薬等でセロトニン(安心)を増やすだけでは片手落ちで
ドーパミンを増やす必要もあるのでは?と考えたりします。
それでは次回は「HSS型HSPの人がモチベーションを維持するには?」
についてお書きしたいと思います。
#HSP(HSC,HSS型含む)のカウンセリングについては
こちらにお書きしてますので、ご参照ください
プロフィール
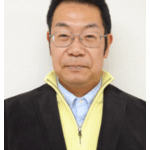
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する