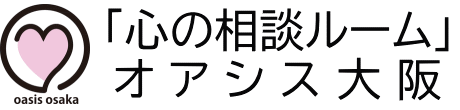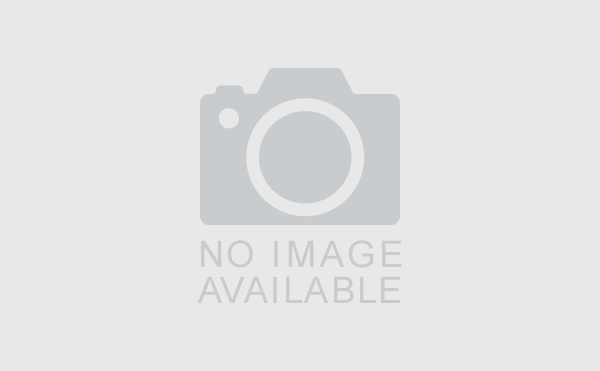何故耐性領域が狭くなり、症状/障害で苦しむのか?
何故耐性領域が狭くなり、症状/障害で苦しむのか?
前回、
「(「ポリヴェーガル理論」を基に考察すると)
”症状”や”障害”と言われるものは、
”腹側迷走神経系”が、
防衛機能を司る”交感神経系”(過覚醒)や”背側迷走神経系”(低覚醒)
を制御できなくなった状態だと考えられる。」
そして、
「腹側迷走神経系が制御不能になってしまう原因の一つは、
耐性領域の狭さであると考えられる」
(耐性領域が狭いから、容易に過覚醒や低覚醒の状態=症状や障害が出現
してしまう)
とお書きしました。
もしそうであるなら、
「耐性領域」は何故狭くなってしまうのでしょうか?
今回は、
考えられるその原因をお書きしたいと思います。
<耐性領域が狭くなる原因>
①愛着(アタッチメント)の問題
耐性領域を広げる為には、
まず幼児期の親との間での自律神経系の「相互調整」を経て
「自己調整」できる能力が育まれる必要があると考えられます。
ところが、
幼児期の養育者との関係においてネグレクトや虐待等によって、
安定型の愛着が形成されなかった場合は、
「相互調整」が行われず、当然自己調整する能力も育まれず、
耐性領域が狭いままになってしまうでしょう。
(恐らく親の過保護・過干渉等によっても自己調整能力は妨げられ、
耐性領域は広がらないと考えられます)
②感覚過敏(過度の敏感さ)
感覚過敏(過度の敏感さ)を有している子供は
元々耐性領域も狭い場合が多いと考えられますし、
例えば
「抱っこやハグされるのが不快」(触覚過敏)、
とか
「わいわいがやがやしている家族と一緒に居るのが不快」(聴覚過敏)、
とか
親の冗談に傷つく、
とか
母親の辛そうな表情を見て甘える事を断念する、
とか
兄妹が怒られる場面を見聞きして親を安全基地とは感じられなくなる、
とか
親や先生のちょっとした注意や誤解、友人のからかい等にも過敏に反応し、
傷ついてしまう
等の、
安定型の愛着が極めて形成し辛い、
即ち自津神経系の調整が極めて難しい状態になる事も多いと想像されます。
それ故、
耐性領域が広がらないケースも多くなるのでは?
と考えられます。
(この感覚過敏については、上記の様な先天的なものもあるでしょうが、
被虐待的な環境に育ったが為に後天的に生じる場合もあると思います。
但しいずれにしても耐性領域を広げられない点では同じだと思います)
それでは、
どうすれば耐性領域を広げる、即ち自律神経系の調整能力を高め、
症状や障害にまで発展しない様にできるのでしょうか?
次回からはそのヒントをお伝えしたいと思います。
プロフィール
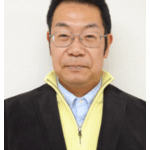
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する