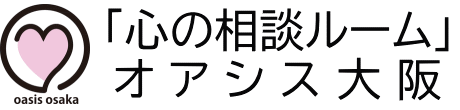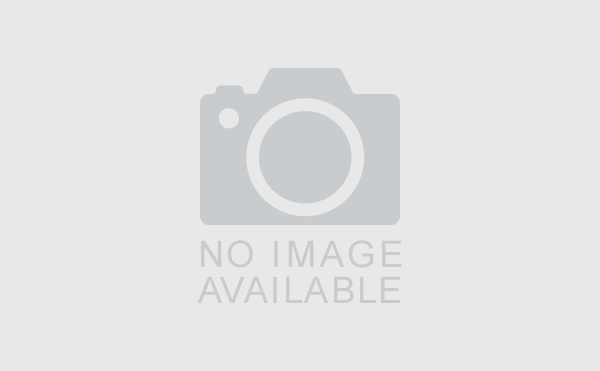カウンセリングのQ&A⑥話を聴いてもらっても変わらないのは何故?
カウンセリングのQ&A⑥話を聴いてもらっても変わらないのは何故?
今回も引き続き、Q&A形式でお書きします。
Q.カウンセリングで話を聴いてもらったのに変わらなかったのは何故?
A.話を聴くだけでは解消できない悩みや症状もあります
前回お書きした様に、
カウンセリングの基本は傾聴や共感、肯定等を通じて、
カウンセラーがクライアントさんの安全基地となって
感情などの相互調整を行い、
クライアントさんが自分の望む人生を再び歩む(探索行動に移る)
様に後押しをする事だと思います。
ところが、そうは行かないケースもあるでしょう。
私は、そういった「話を聴くだけでは前へ進めない」ケースには
以下の原因があるのでは?と考えております。
<話を聴くだけでは改善しない場合の原因>
①自己調整能力が育っていない場合
例えば、
幼い頃の母親等、養育者との間で
「安定型の愛着」が形成されていなかった場合は、
心の安全基地を持てずに
感情(⇒思考⇒行動)の相互調整がなされていなかったはずです。
相互調整を経ないと中々身につかないであろう
感情(⇒思考⇒行動)を自己調整する力、
即ち自分で自分の機嫌を取る事が難しくなるでしょう。
そうなると、
「話を聴いてもらった時はすっきりしたけど、
家に帰るとまた不安に襲われ続ける」等といった事が起きるでしょうから、
「カウンセリングを受けても結局何も変わらない」等と、
通うのをやめるか、
逆にカウンセラーに依存してしまう人もいらっしゃると思います。
そういった場合は、
クライアントさんが「自己調整能力」を身につける為のお手伝いが必要
だと思います。
②自己調整能力はあるが、耐性領域が狭い
ある程度感情(⇒思考⇒行動)の自己調整能力は持っていても、
例えば過度の敏感さ等から、すぐに耐性領域を超えて「過覚醒」となり、
パニックや不安、怒り等の感情に呑み込まれてしまう(交感神経系が
制御不可になる)、
或いは
「低覚醒」になり、部屋に引きこもってしまったり、身体が動かなくなる
(背側迷走系が制御不可になる)等の場合も、
話を聴いてもらうだけでは
”カウンセリングを受けたその場だけ”の安心・安全に終わってしまう
でしょう。
そういった場合は、
クライアントさんの”耐性領域”を拡げ、
すぐに過覚醒や低覚醒に陥らない様なお手伝いが必要だと思います。
③耐性領域を超えてしまうトラウマ等を抱えている
トラウマ(単回性、 複雑性)を抱えている方は、
普段は感情(⇒思考⇒行動)の自己調整能力を発揮できていても、
例えばトラウマのフラッシュバック等が起きると、
耐性領域を超えて「過覚醒」となり、
パニックや解離、恐怖、自責、無力感、恥、怒り等の感情に
呑み込まれてしまう(交感神経系が制御不可になる)、
或いは
「低覚醒」になり、部屋に引きこもってしまったり、身体が動かなくなる
(背側迷走系が制御不可になる)等の場合も、
”カウンセリングを受けたその場だけ”の安心・安全に終わってしまう
でしょう。
そういった場合は、
クライアントさんのトラウマをケアしながら、
感情(⇒思考⇒行動)の自己調整能力を高めて”耐性領域”を拡げ、
トラウマによる過覚醒や低覚醒に呑み込まれない様になる為のお手伝い
が必要だと思います。
プロフィール
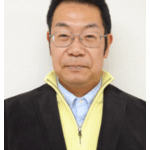
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する