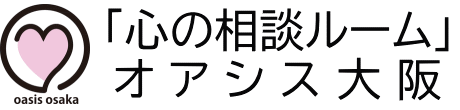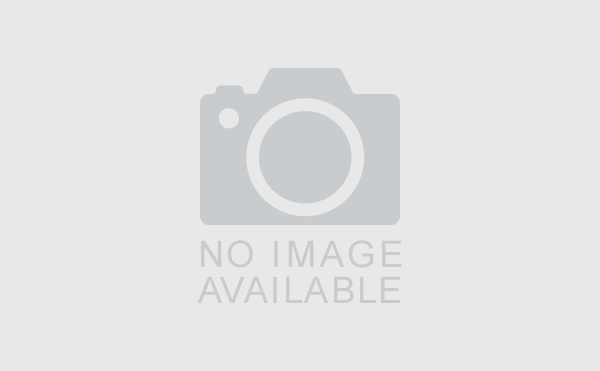どうすれば新しい環境に順応できるのか?①環境の調整
どうすれば新しい環境に順応できるのか?①環境の調整
「感覚過敏」(そこから来る「プチトラウマ」や
「不快刺激を無くす事で安定する傾向」)を有している為に
新しい環境に身を置く事に恐怖を感じる人はどうすれば良いのでしょうか?
そのヒントを今回からお書きしてゆきたいと思います。
まず、
「感覚過敏」は多くの場合は先天的・遺伝的なものだと考えられます。
ですから、
「気にし過ぎない様にすればよい」等のアドバイスは
敏感な人に向かって、”鈍感になれ!”と言っている様なものですので、
役に立たないどころか「気にしてしまう自分」を益々否定的に捉えてしまい
更なる自己肯定感の低下につながるでしょう。
だとすれば、
”そこ”を変えようとするのではなく、
「環境の調整」と「内面の調整」が役に立つでしょう。
今回は「環境の調整」から。
<新しい環境に順応する為のヒント①環境の調整>
(1)五感から入ってくる(不快)刺激を減らす
例えば、
・「度が合っていない眼鏡や、色付きの眼鏡をかける」(視覚)
・「前髪や帽子によって視覚の制限をかける」(視覚)
・「イヤーマフやノイズキャンセリングを使用する」(聴覚)
・「お気に入りのガムを噛む」(味覚・触覚・嗅覚)
・「肌触りの良い下着をつけたり、
触り心地の良い小さなぬいぐるみ等を身につける」(触覚)
・「好きな感触で、お気に入りの香りをつけた大きめのマスクをする」
(触覚・嗅覚)
等々。
※これらは、職場や学校の方の理解が必要ですし、
やり方によっては悪目立ちしてしまう不安も生じるでしょうから、
難しいものもあると思います
(2)(不快)刺激を受けない時間・空間を作る
例えば、
・「大講義室では、一番後ろの隅の席に座る」
・「パソコンを置く位置を工夫したり、自分のデスクの周りに
書類等を積み上げ周囲の人の視線をガードする」
・「トイレに籠る時間を敢えて作る」
・「職場や学校の近くに、お気に入りのベンチ等を見つけ、
休憩時間等には頻繁にそこを利用する」
・「(学生なら)クラブやサークル、ゼミ等の
少人数で快適さを感じる場(安全基地)を作る」
・「(社会人なら)一緒に昼休憩を取る人や信頼できる先輩・上司、
(職場では難しい場合は)同窓生や趣味のサークルなど、
少人数で快適さを感じる場(安全基地)を作る」
等々。
※私が思うに、「感覚過敏」から来る生き辛さを抱えた方に対して、
”合理的配慮”としての環境の調整は知られてきていると思いますが、
ご本人側の「安全基地」作りといった能動的な働きかけに加えて、
内面の調整も大切な事だと思います。
次回はそれについてお書きしたいと思います
プロフィール
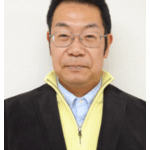
- 心理カウンセラー・自己実現コーチ
- ・公認心理師
・全国WEBカウンセリング協会認定
心理療法カウンセラー
不登校児対応アドバイザー
・矢野惣一「心の専門家養成講座」卒業
NLP、催眠療法、ゲシュタルト療法、解決志向ブリーフセラピー、フォーカシング、認知行動療法ナラティブセラピー、インナーチャイルド癒し、トラウマ療法、家族療法(システムズアプローチ)等とその統合を習得する(TVの解決ナイナイアンサーでお馴染みの「性格リフォームの匠(達人)」心屋仁乃助さん、「アネゴ系セラピスト」大鶴和江さんは矢野講座の先輩です)
・Gakken「学研の家庭教師」不登校事業室の外部相談カウンセラー
・WEBカウンセリングルーム「みらい」カウンセラー
・日本フォーカシング協会会員
・国際ブリーフセラピー協会(旧:日本ブリーフセラピー協会)会員
2012年2月開業。2025年時点で4,000名超のお客様のご相談をさせて頂きました。
最新コラム
- 2026年2月20日ブログ発達障害(ASD,ADHD等)の本当の原因を探る①共通しているものは?
- 2026年2月13日ブログ発達障害(ADHAD=注意欠如多動症)の定義(診断基準)
- 2026年2月6日ブログ発達障害(ASD=自閉スペクトラム症)の定義(診断基準)
- 2026年1月30日ブログ発達障害(ASD,ADHAD等)の全てを解明する