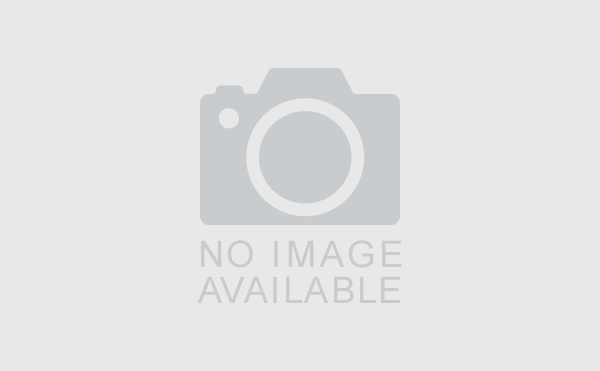意欲に欠ける生徒や部下を持った人へ
意欲に欠ける生徒や部下を持った人へ
「あの子は学習に取り組む意欲が全くない」
という親や先生や
「私の部下は仕事に対する意欲が感じられない」
という上司。
「意欲」とは、「欲求」と「意志」が揃って働いて
初めて目に見える言動に現れてくるものです。
そして「欲求」とは「快」の感情を求め、
或いは逆に「不快」な感情を避ける為に行動に駆り立てる力の事を言います。
一方「意志」とはその欲求を行動として現すか、それとも抑えるか、を決定する
ものです。
ですから、単に「意欲がない」と言っても「欲求」がそもそも無い場合と
「意志」がそれを抑えようとしてしまってる場合とがあるはずです。
そしてこの「欲求」は動機づけがきっちりなされているか?にかかってくる
と思いますし、「意志」は不安の影響を受けると思います。
(※そもそも「欲求」自体が本人のものではなく、親や教師、上司のもの
である場合は、本人の欲求としていかに動機づけがなされるか?が大切
だと思います。
ただ、いくら動機づけをしようとしてもできない場合は、
親や教師、上司の欲求自体を変えてゆく必要があるでしょう)
ー 例えば、
「勉強しないと、あなたの望む人生は手に入らないわよ」
というスタンスで子供を励ましてきた親がいるとします。
これでこの子は「不快」な感情を避ける為に「意欲」が出て勉強する訳です。
所が、そのうちに「親の言う通りにしている自分て何なんだろう?
将来どうなっちゃうんだろう?」という不安や
「確かに勉強はできる様になったけど、クラスで浮いちゃってる。
どうしたら友達できるんだろう?」等と、それ以上の不安が頭をもたげて来て
「意志」が「欲求」に”待った”をかける訳です。
その様に、そもそもの動機付けの段階で「〇〇しないと△△になってしまうぞ」
とやってしまうと(負の動機付け)「不快」を避ける為の欲求ですから、
常に不安と隣り合わせになってしまいます。
というのは「欲求」という前提自体が不安に支配されていますから、
「意志」も不安ばかりを拾って、それを避ける為に”負に動機づけられた”欲求
ばかりを増やしてゆくでしょう。そして身動きできなくなる・・・。
※勿論そんな中でも意欲を失わず目標を達成する ”強者”もいるでしょうが・・。
では、「欲求」自体を「快」の感情を求めるといった「正の動機づけ」に
変えれば意欲は保ち続けられるのでしょうか?
これも、一概にそうだとは言えないと思います。
確かに「〇〇をすれば△△が手に入る」という動機付けはいいとは思いますが、
それが手に入らなさそうだと感じたり、興味を失ったり、逆に手に入ってしまった時
に「意志」が待ったを掛け、「欲求」がしぼんでしまうでしょう。
そういった時には
「それをしたらどうなれる?何が手に入る?」
「それをしなかったらどうなっちゃう? 何を後悔する?」等と
再度動機づけを促すか、
「本当はどうしたいの?どうなりたいの? 何が欲しいの?」
「そうなったとしたら、どんな気分になる?」
等と、新たな欲求を喚起させるか、という援助が必要だと思います。
そして、動機付けされた「欲求」が作られれば
「それを達成する為に行動するとして何が不安?」
「その不安を少しでも減らす為にはまず何ができる?」
等と「意志」の不安を取り除く援助も必要かも知れません。
つまり、大切な事は常に「負」の動機づけ一辺倒や「正」の動機づけ一辺倒
にならない様にバランスを取り、必要とあらば再度「欲求」を見直してゆき
変えて行く事。 「欲求」に”待った”をかける「意志」の不安をあぶり出し、
その不安を少しでも和らげる策を一緒に考えて実行してもらう、
という事だと思います。