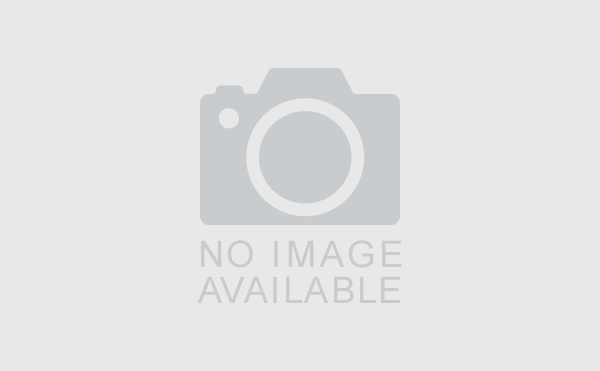仕事が続かない人へ③性格傾向(3)白黒思考
仕事が続かない人へ③性格傾向(3)白黒思考
今回と次回は
極端な「白黒思考」によって仕事が続かない方
に向けてお書きしたいと思います。
<極端な白黒思考によって仕事が続けられなくなる例>
「営業部のD男さんはバリバリ頑張るタイプで、
自分の成績が部内で一番だった時には明るい表情で饒舌になるが、
成績が良くない時や、顧客からクレームが入った時には、
途端に表情が暗くなり、無口になってしまう。
やがて彼の頑張りが認められて、
”主任”として新入りのE君の面倒を見る事になった・・・。
ところがE君は、
今どきの”仕事よりもプライベートを充実させる”タイプで
D男さんから見ても余りやる気を感じなかった。
だからD男さんは”何やってんだ?もっとやる気を見せろ!”
等とE君に口酸っぱく言う様になった。
そんな或る日、明日の訪問先の準備もそこそこに、
定時で帰ろうとしているE君に業を煮やしたD男さんは、
”お前!仕事を舐めてんのか?!・・・
この前の訪問でも、大事な資料を用意してなかっただろう?!
今日は何時になってでも明日の準備を完璧にしろ!!”
と、つい声を荒げてしまった。
翌日D男さんは部長に呼ばれ、
E君が”主任からパワハラを受けたので辞めたいです”と言ってきたぞ!”
と注意された。
それを聞いたD男さんは、
”あ~、どの営業会社へ行っても、他人を管理する立場になると
俺はダメだな・・・”と一気に落ち込んでしまい、
転職が頭の中をよぎった」
<仕事が続かない原因③性格傾向(3)極端な白黒思考)>
(1)刺激(快・不快)への感受性が過度に強い(感覚過敏)
誰しも、
「頑張って何かを達成した」=”快”
「頑張れなかった為に未達成に終わった」=不快
「きっちりできて、優秀な成果を上げた」=快
「きっちりできなくて、成果を上げられなかった」=不快
「ミスしてしまった」=不快
だと思います。
ところが、
(多くの場合は生まれつきに)刺激(快・不快)への感受性が過度に強い人は、
それらの”快/不快”刺激に対して非常に敏感である、と考えられます。
(2)刺激(快・不快)への敏感さが、ある特定の方向へ偏った
例えば上記のD男さんの場合は、
「頑張ってる/頑張ってない」
「きっちりできてる/できていない」
「優秀である/ない」
「ミスする/しない」
等の特定の方向へ偏っていると考えられます。
(例えば仕事はミスなくきっちりしていても、整理整頓はいい加減
なのかも知れませんし、勉強や仕事は優秀である事に拘るが、
スポーツはそうではなかったりするかも知れません)
そして恐らくこの”偏り”は
幼少期の体験から方向性が決められたと想像されます。
例:
・学校の成績に拘る親だった
・失敗やミスに纏わるトラウマチックな体験
・成績やきっちりさを褒められた快の体験
・親等の尊敬する人の影響
等々。
(3)信念の固定
上記「(1)」「(2)」によって
自分にとっての避けるべき”不快”と求めるべき”快”が決まったら、
刺激(快・不快)に対して、過度の敏感さを有している人は、
「”絶対に”不快を避けなきゃ!」
(通常、快を求める事よりも不快を避ける事が優先される筈です)と、
自分なりの信念を形作るでしょう。
例えば、
「頑張らなきゃいけない」
「きっちりしなきゃいけない」
「優秀でなきゃいけない」
「ミスしてはいけない」
等。
そして、
そこに拘る事でしか不快を避ける術が無いとすれば、
その信念はより強固になってゆくでしょう。
それ故、
その信念に少しでも反する事は「アウト」になってしまい、
「0か100か?」「白か黒か?」といった極端な考え方になってゆき、
自らも縛られますが、他人をも縛ってゆくのだと思います。
もし、そうだとすれば、
「極端な白黒思考)」によって仕事が続かない方
はどうすれば良いのでしょうか?
私なりに考える解決策のヒントを次回お書きしたいと思います。