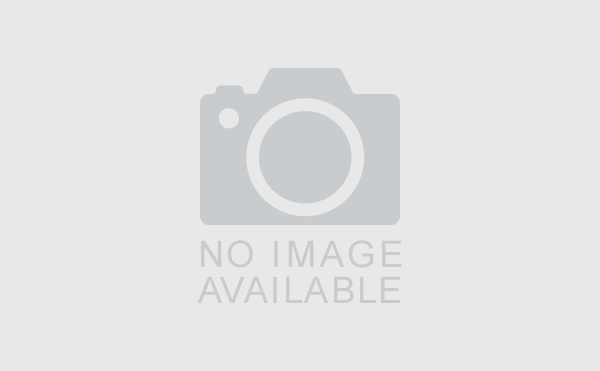症状/障害を制御する能力の高め方②
症状/障害を制御する能力の高め方②
<前回からの続き>
<症状/障害を制御する能力の高め方②>
②相互調整能力を高める
「相互調整」とは
本来、安定型の愛着が形成された親子に見られる様な
「泣いてる子に親が笑顔で抱っこする」
⇒
「子が笑顔になってはしゃぐ」
⇒
「それを見た親も安心する」
等といった、
自律神経系や感情の双方向の調整です。
だとすれば、
交感神経系や背側迷走神経系による過度の防衛反応が生じている人
だけではなく、
依存/共依存的な一方通行の調整しか行っていない人にも
相互調整能力を高める事は有効だと考えられます。
(1)過度の防衛反応が生じている人
(「①」の自己調整能力を高めながら)
まず、
過度の防衛反応が出ない人を選んでゆく。
そして、
その相手に思い切って不安や悩みを打ち明けて、
自分の感情を調整してもらう。
(その時の相手の感情の変化も感じる様にする)
次に、
相手の不安や悩みを聞いたり、
相手が「落ち込んでるか?、興奮し過ぎてるか?」に気が付けば、
こちらが元気づけたり落ち着かせたり、等の感情を調整してあげる。
(その時の自分の感情の変化も感じる様にする)
(2)依存/共依存的な人
依存的な人(相手に自分の感情を調整してもらう)も、
共依存的な人(相手の感情を調整しようとしてしまう)も、
感情調整から言えば、
一方通行になっていると言えるでしょう。
ですから、
依存的な人は
「相手の感情を調整しようとトライする事」
が相互調整へと繋がるでしょうし、
共依存的な人は
「自分の感情を相手に調整してもらおうとトライする事」
が役に立つと思います。
次回はこの続きである
「腹側迷走神経系が働く機会を増やしてゆく」ヒント
をお書きします。