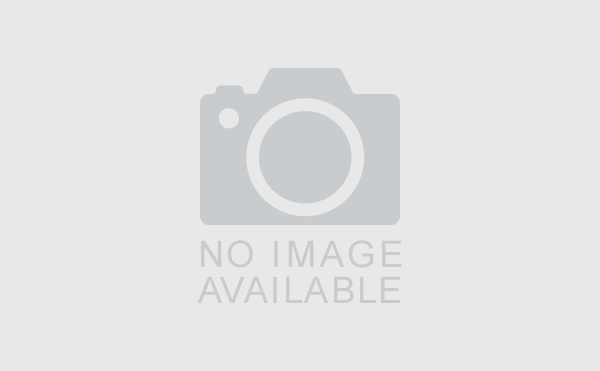カウンセリングのQ&A⑤カウンセリングは話を聴くだけ?
カウンセリングのQ&A⑤カウンセリングは話を聴くだけ?
今回も引き続き、Q&A形式でお書きします。
Q.カウンセリングは話を聴くだけ?
A.カウンセラーの依拠する学派によって異なります
そもそも、現在の様な形での”カウンセリング”の礎を築いたのは
アメリカの臨床心理学者であったカール・ロジャーズです。
彼のカウンセリングでは、
相手の話を”傾聴”し、
相手の気持ちや考え方に共感し相手を肯定的に受容する、
という事に主眼が置かれていました。
彼のカウンセリングが日本に”輸入”されて以来、
カウンセリング=傾聴と言われる位に大きな影響を与え続けています。
心理カウンセリングを志す人にとっては、ロジャーズの学派は基本であり、
大学でロジャーズ学派の先生に師事してきた心理士、心理師も多い
と思いますので、
日本では今も多くのカウンセラーは傾聴メインになっていると思います。
ここからは私の考えですが、
ロジャーズの「傾聴」、
そして
彼のカウンセリングにおける3原則である
「共感的理解」、「(相手への)無条件の肯定的関心」、「自己一致」は
時代や学派を超えて、今もカウンセリングにおいては必須のもの
だと思います。
何故なら、
彼がやろうとしていた事は、
「ポリヴェーガル理論」で言う所の
社会的関わりの機能を持つ「腹側迷走神経系」に働きかけ、
過度の防衛反応によって症状や障害をもたらす「交感神経系」や
「背側迷走神経系」の制御機能を取り戻す事を目的としていた、
と言えるのではないか?と思います。
※「愛着理論」の観点からは、
カウンセラー自らがクライアントの”安全基地”となって
クラインとの感情の”相互調整”を図り、
クライアントが本来持っている自身の望む人生を生きる(探索行動)力を
取り戻す事を主眼にしているとも言えるでしょう
ところが、
「カウンセリングで、話を聴いてもらうだけでは何も変わらなかった」
という方も多いのも事実です。
それは一体なぜなのでしょうか?
次回は私が考えるその原因をお書きしたいと思います。