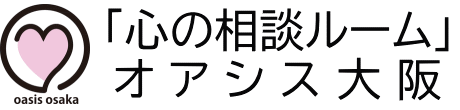劣等感
自己嫌悪・劣等感の正体
「あ~・・・私は勉強もできないし、人付き合いもうまくできずに、 友達や彼氏もできない。 自分の顔も性格も嫌い・・・ こんな私って、生きている意味があるのかなあ~」 「僕はクラスの他の男子みたいに他人と気軽に話せない […]
希死念慮にも2種類ある?
<前回からの続き> 前回お書きした通り、私の推測では「うつ」には ① 「N」「(ノル)アドレナリンシステム」 (=恐怖・不安・怒り・行動化)」 →「S」「セロトニンシステム」 (=安心・安定・幸せ・満足 […]
抗うつ薬が効かない人へ~うつには2種類ある?
<前回からの続き> うつ病も含めて、精神疾患は主な原因として、 心因性・内因性・外因性と分けることができます。 ただ、現在の医師の診断基準となる「DSM」や「ICD」では 原因よりも表に現れている「症状」から診断が成され […]
劣等感とうつ病(劣等感に意識を向けて”うつ”を作り出す)
<前回からの続き> 今回は「劣等感とうつ病」について、 架空のA子さんを例にしてお書きしたいと思います。 A子さんは中学受験をし、 この春から自宅から少し離れた私立中学に通う事になりました。 A子さんは文系 […]
劣等感と自己愛性パーソナリティー障害②
<前回からの続き> 今回は前回取り挙げた、「自己愛性パーソナリティー障害」と思しき 架空のA男さんの心理(脳)的なメカニズムを(私見に基づき)解説して ゆきたいと思います。 A男さんは父親に否定され、モラハラ・DVを受け […]
劣等感と自己愛性パーソナリティー障害①
<前回からの続き> 今回も引き続き、 「刺激を求める傾向が強い人は ”ドーパミンシステム”、”(ノル)アドレナリンシステム”優位型 と考えられる。 そういったタイプの人は、刺激不足に陥ると”劣等感”や”怒り”、”不 […]
劣等感と摂食障害(拒食・過食)
<前回からの続き> 前回、 「刺激を求める傾向が強い人にとっては、退屈が苦痛になる」 「刺激を求める傾向が強い人(=”ドーパミンシステム”+ ”(ノル)アドレナリンシステム”優位型)は、 「劣等感」や「怒り」、「不安」を […]
劣等感や怒りや不安を作り出す人
<前回からの続き> 前回、マズローの欲求5段階説を基に 「社会的欲求」や(人間のみが有すると思われる)「承認欲求」は 他人と比べて劣ってるといった「劣等感」が形成されないと 不快刺激とは認識されずに、(ノル)アドレナリン […]
劣等感は欲求を満たす為に作り出される?
<前回からの続き> 前回私の推測として、 「人は”報酬”を得る為に敢えて劣等感を作り出す (或いは劣等感に意識を集中する)事さえあるのでは?」 とお書きしました。 もしそうだとすれば、何故わざわざ「劣等感」を作り出したり […]
劣等感を快感に結びつける
<前回からの続き> 前回、「劣等感を克服する」一方法をお書きしましたが、 その”ミソ”(ポイント)は”快”(ドーパミンのシステム)を利用する事 だと思います。 どういう事かと言いますと、 例えば、「人には白血球の血液型と […]
劣等感を克服(活用)するには?
<前回からの続き> 前回お書きした様に、 「劣等感」とは「自分が持ちたいと望んでるものが、今は未だ得られていない から生じるのであって、そこにはそれを得たいという強い欲求がある」。 そして、 それは人間(遺伝子?)にとっ […]
劣等感は遺伝子に組み込まれている?
「あの娘は、いつも明るくてみんなの人気者だ・・・ それに比べて私はネガティブでいつも独りぼっち・・・ 本当はみんなと仲良くしたいのになあ~・・・。」 「同僚のA子は仕事ができて、いつも上司に褒められてる。 それに比 […]
相手(の怒り)に支配される人②
(前回の「相手(の怒り)に支配される人①」からの続き) 前回「自分側のパターンを変える」と書きましたが、 脳の認知(インプット)~行動/反応(アウトプット)の流れとして、 A.環境からのインプット(例=会社・夫婦・相手) […]
相手(の怒り)に支配される人①
「何で言われた通りにできないんだ!」等と上司に怒鳴られ →「す、すみません・・・」と委縮したら、 →「いつも、すみませんばっかりで本当に反省してるのか?!」と 机を叩かれて増々委縮してしまう。 「こうなったのもあなたの […]
倒れるまで頑張り過ぎてしまう人へ
「誰にも甘えずに休日返上で仕事をやり続けて うつになって動けなくなりました・・・」 「家事と育児を完璧にやろうとして、 イライラが溜まって夫に当たったり、 過食や買い物依存に襲われています・・・」 周囲の人から 「 […]
自尊感情と劣等感~自分と他人を比較しましょう
人間の成長とは、ある意味では「他人と自分の違いを知る」事だと思います。 そして”違い”を知れば「全く別の人格や個性を持つ存在として自分と他人を認め お互いを尊重してゆく」というのが理想形だと思います。 そしてまず「違いを […]